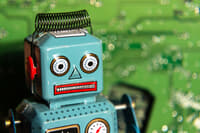中国「音響攻撃」説は本当か......米政府職員が脳損傷

「軽度の外傷性脳損傷」と診断された職員が勤務していた広州の米総領事館 Wonry/iStockphoto
<2017年にはキューバで同様の事件があったが、どちらも粗悪な盗聴装置が原因の可能性あり>
在中国の米大使館は5月23日、ある職員から「最近、かすかで曖昧だが、異常な音と音圧を感じたという報告があった」と発表。中国在住のアメリカ人に注意を呼び掛けた。「異常な音またはノイズによって聴覚や知覚に著しい異常を感じた場合、その音が聞こえない場所に移動してください」
米大使館の報道官はCNNに対し、この職員は広州の総領事館駐在で、「軽度の外傷性脳損傷」と診断されたと語った。
その後、ポンペオ米国務長官はこの出来事について、16〜17年にキューバの首都ハバナで米大使館の職員に発生した健康被害と「酷似」していると主張。当時、米国務省は大使館職員の大半を帰国させ、キューバ政府による「音響攻撃」を非難した。
今回もアメリカのメディアは中国による「音響攻撃」と報じたが、多くの研究者はその可能性は低いと考えている。
ドルトムント工科大学(ドイツ)の実験物理学者ユルゲン・アルトマンは、CNNにこう語った。「脳震盪のような症状を引き起こす音響効果など、聞いたことがない。人体に強い影響を及ぼすレベルの音なら、そのときに大音量のノイズが聞こえるはずだ」
キューバの事件についても、多くのアメリカの専門家は「音響攻撃」説に懐疑的だ。例えば、ハバナの大使館職員21人を調査したペンシルベニア大学の研究チームは米国医師会報の論文で、脳の障害の原因とされる説は(音響兵器説も含め)、どれも合理性を欠くと示唆している。FBIも、音響兵器説を裏付ける証拠はないと認めている。
中国側の反応は抑制的
一部の研究者は、むしろキューバの事件は「盗聴活動が生んだ偶然の副作用」の可能性が高いと主張している。
ミシガン大学のケビン・フーは中国・浙江大学の研究者2人と共同で、この問題を分析した論文を発表した。同大の広報メディア「ミシガンニュース」によると、研究チームは実験を通じ、盗聴装置から出る超音波信号は「潜在的な危険性をはらむ可聴帯域の音を生成する場合がある」ことを示した。
「私たちは、(外交官の)健康被害は秘密作戦に使われた粗悪な超音波送信機の意図せざる副産物だったのではないかという説を提示した」と、フーはミシガンニュースに語っている。「音響兵器が使われた可能性よりも、超音波を使って情報をこっそり盗み出したり会話を盗聴するための装置の不具合と考えるほうが説得力があると思う」