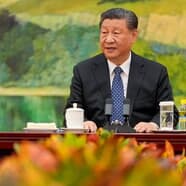トイレの前でズボンを脱ぎ、下半身パンツ1枚で待つ。これが刑務所生活の実態だ

Newsweek Japan
<「仮入所体験」ができると謳う『もしも刑務所に入ったら』の著者は、「日本一、刑務所に入った」という法社会学者。意外に思える刑事政策の基本姿勢も知ることができる>
『もしも刑務所に入ったら――「日本一刑務所に入った男」による禁断解説』(河合幹雄・著、ワニブックスPLUS新書)のカバーには、「本だからできる、仮入所体験」と書かれている。正直なところ、最初はこれをちょっと大げさだと感じた。
ところが確かに、読み進めていくと"入所して、そこで生活している"ような気分になってしまった。そして、「もし本当に、こんな所に入れられることになったらどうしよう」と、軽い不安を抱いたりもした。
だが著者はそもそも、"そういう本"であることを「はじめに」の段階で明らかにしていたのだ。
さて、本書の狙いだが、
「どんなことをすると刑務所に入れられるのか?」
「刑務所とは一体どんな場所か?」
「刑務官という職種はどんなものなのか?」
という刑務所にかかわるさまざまな疑問に答えるものである。
(中略)あくまで、小難しいアカデミックな話は抜きにして、入所から退所するまでの流れや、受刑者たちの生活実態、そして刑務所の現状を平易な言葉で追うこととする。(「はじめに」より)
つまり、「受刑者の社会復帰のために刑務所が果たす意義」というような難しいことが書かれているのではなく、「収監までのプロセス」「刑務所の種類」「そこで行われていること」などが淡々と紹介されているだけなのである。
読者はそれを受け止めるしかなく、だから結果として妙なリアリティを感じてしまうのだ。
ちなみに著者は法社会学者だが、自身について次のように記している。
私は法務省矯正局関連の公益法人の評議員や刑事施設視察委員会委員長として、刑務所はもちろん、少年院や女子少年院など、全国各地の矯正施設を視察してきた。言い換えれば、「日本一、刑務所に入った男」と言っても過言ではない。(「はじめに」より)
そんな著者によれば、実際のところ刑務所は、そう簡単には入れない仕組みになっているという。「悪いことをすれば警察に捕まり、刑務所に放り込まれる」というような、単純なものではないということだ。
刑事政策上の基本姿勢は、「なるべく入れない、入れてもすぐに出す」。そのため、万引きなどの軽微な犯罪(それでも立派な犯罪だが)であれば、3回までは許されてしまうそうだ。
ということは4回目が分かれ目になるということだろうが、検察や裁判所が起訴猶予や執行猶予という判断を下せば、当然のことながら刑務所には入れないわけだ。
しかも入れられたとしても、死刑囚を除けば犯罪者はいつか実社会に出てくるものでもある。
とだけ聞くと、刑事政策は甘いと感じるかもしれない。だが、それを考えるにあたって無視できないのは、刑務所が「矯正施設」であるという点だ。その目的は、収容者の更生と社会復帰なのである。