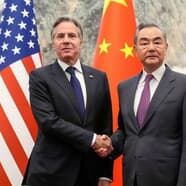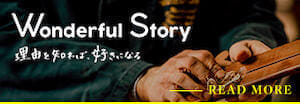- HOME
- コラム
- リアルポリティクスNOW
- 「野党共闘」の射程を戦略的パートナーシップ論から読…
「野党共闘」の射程を戦略的パートナーシップ論から読み解く
「分水嶺だった」と言われる(かもしれない)共闘
これに対して、野党共闘を構成する共産党に焦点を当てて、同党を一種の「禁断の果実」になぞらえる直接的な批判もある。先述した自民党広報はその一例だ。全国的に組織を有する共産党の基礎票を当てにした立憲民主党が「禁断の果実」を食べたというのである。戦後政治史上もっとも成功した戦略的パートナーシップは、野党時代を挟んで通算20年近く連立政権を維持している現在の「自公連立」だと考えられるが、その自公連立も当初は大きな批判を浴びた。しかし、政権を獲るという戦略的利益のために「政治的な戦略的パートナーシップ」が構築される場合、食べた果実が「禁断」のものと評価されるかどうかは結果次第とも言える。「禁断の果実」を食べて楽園から追放されることになるのか、それとも「知恵」を手に入れて新たな楽園を築くのか――。
いずれにせよ今回の野党共闘は後世になって「あれが分水嶺だった」と言われる可能性がある潜在的な重要性を有している。むろん現在の立憲民主党側は、山本太郎・れいわ新選組代表の選挙区変更劇(東京8区から比例東京ブロックへ)に象徴されるように、左派ポピュリズムに徹し切れず、戦略的パートナーシップの本領を発揮できていない弱点も持っている。しかし、グローバル化とデジタル化に伴う社会構造の変化の中で没落した「中間層」の民意をリベラル側からすくい上げる対抗的ベクトルが今形成されつつあるとしたら、自公連立側にとっては本質的に大きな脅威となり得るだろう。およそ「国共合作」の故事を示唆する攻撃だけでは、それほど有効な批判にならないかもしれない。
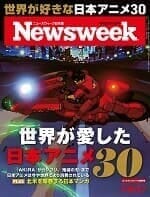
アマゾンに飛びます
2024年4月30日/5月7日号(4月23日発売)は「世界が愛した日本アニメ30」特集。ジブリのほか、『鬼滅の刃』『AKIRA』『ドラゴンボール』『千年女優』『君の名は。』……[PLUS]北米を席巻する日本マンガ
※バックナンバーが読み放題となる定期購読はこちら
乾坤一擲の勝負に出た岸田首相、安倍派パージの見えない着地点 2023.12.19
政権直撃のパー券裏金問題と検察「復権」への思惑 2023.12.09
「パー券」資金還流問題、議員のノルマとキックバックと重大な嫌疑 2023.12.06
コンプライアンス専門家が読み解く、ジャニーズ事務所の「失敗の本質」 2023.09.15
岸田首相の長男にボーナスは支払われる 2023.05.30
岸田首相襲撃で「テロリズム連鎖の時代」が始まるのか 2023.04.15