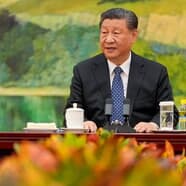ダイアナ死去で犯した間違い、好きだった英首相・米大統領... 元BBC記者が書くエリザベス女王の96年
A QUEEN FOR THE AGES

エリザベス2世は英連邦の全ての民のために努力すると約束した(1993年撮影) THOMAS IMO-PHOTOTHEK/GETTY IMAGES
<9月19日に国葬が行われるエリザベス2世。彼女は他人と打ち解けず、感情を表に出さない英国人だったが、儀礼的な務めをこなし続け国民との絆を深めた。時代と共に歩んだ君主の在り方は新国王で変わるのか>
幼い頃のエリザベス・アレクサンドラ・メアリーは、まさか自分が大英帝国(と、その広大な植民地)に君臨する日が来るとは夢にも思わずに育った。
当時の国王は伯父(エドワード8世)で、王座は彼の娘か息子が継ぐはずだった。
ところが伯父は世継ぎを残さず、「恋に生きる」と宣言して王位を返上。やむなく弟(エリザベスの父)がジョージ6世として即位した。この瞬間、エリザベスの運命は急転し、ジョージ6世の長女として王位継承順位1位となった。
それから戦争が始まり、終わり、父が逝去して、彼女は25歳の若さで女王エリザベス2世となった。その後も国内外で(そして家庭内でも)荒波にもまれ、時代に翻弄されたが、負けずに一本の筋を貫いた。
そして9月8日に、96歳で世を去った。
彼女は他人と打ち解けず、感情を表に出さなかった。昔なら最高とされた英国人気質だが、洗いざらい何でもさらけ出す今の時代には不適切に見えたかもしれない。
だが記念碑の除幕や勲章の授与、外国要人の接遇(政府の要望に応じて、おだてもすれば懐柔もした)など、儀礼的な務めを淡々とこなし続けることで国民との絆を深めた。ロイヤル・アスコット競馬場で女王の愛馬が優勝すれば、必ず大きな歓声が上がったものだ。

そんなエリザベス2世の時代が終わった。この先、イギリスの君主制はどこへ行くのだろう。
長年にわたって棚上げにされてきた諸課題が、改めて浮上してくる。
もちろん今の世界は、彼女がアフリカの植民地ケニアで父の訃報に触れた1952年2月から様変わりしている。
現時点で英連邦に含まれるのはカナダ、オーストラリア、ニュージーランド、その他11の地域のみ。かつて大英帝国の「所有物」とされた多くの植民地は独立し、英連邦からも離脱している。
歴代の首相に寄り添って
在位70年の間に接した英国首相は15人。意外なお気に入りは、イングランド北部出身の平民で社会主義者だった労働党のハロルド・ウィルソンだ。
1960~70年代に首相を務めたウィルソンは、謁見の席でパイプを吸うことを許されたという。アルツハイマー病で退任を覚悟したと聞くと、女王は特別な対応で彼の労に報いた。首相官邸に自分を招き、夕食を振る舞ってくれと提案したのだ。
直近14人のアメリカ大統領のうち、13人とも会った。第33代のハリー・トルーマンとは即位前の1951年に会った。
ウマが合ったのは第34代のドワイト・アイゼンハワー。女王は彼に、自分の好物スコーンのレシピを送っている。