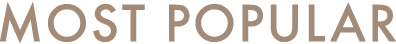Jirsak-shutterstock
萩原朔太郎が「ふらんすへ行きたしと思へども/ふらんすはあまりに遠し/せめては新しき背廣をきて/きままなる旅にいでてみん。」(「旅上」『純情小曲集』1925所収)と詠ってから百年近い歳月が流れている。
この時の経過は、渡仏を遥かに容易なものに、換言すれば「きままなる旅」の目的地としてフランスを選ぶことを可能にした。そのことは、長木誠司による『アステイオン』99号特集「境界を往還する芸術家たち」の巻頭論文「ヨーロッパで活動する日本人音楽家」に記された、海外で活躍する多くの日本音楽家の様子に端的に示されているだろう。
交通手段の発達そして日本経済の発展が、こうした越境を容易なものにした。しかし、科学技術や経済という下部構造の変動に由らずとも、人は、想像力により、何より言葉の力によって、自身がいる現実から飛翔し、異境の地へと赴くことができる。
上野誠+ピーター・J・マクミラン+張競による鼎談「境界を往還する万葉集」でマクミランや上野が指摘する『万葉集』の持つ呪術性こそ、言語によって人が現実から飛翔する力を指し示すものだと言えよう。
上野は『万葉集』における「見れば見ゆ(見たら見えた)」という型の国見歌は、現実の風景が歌に描かれたものと異なるもの、時にそれは正反対の景色であっても、歌に詠み込まれるとその情景が実現への過程を歩み始める、そういう力を持っていると言う。
歌は、言葉は、人を現実から、それがどんなに悲惨なものであっても、「美しい」世界へと舞い上がらせる力を帯びている。
テクノロジーや経済力といった「物理的」力に由らずとも、人には越境が可能であったとすれば、百年ほど前の朔太郎とて、「新しい背廣を着」ることで眼前の日本の景色をフランスのものへと転換し、越境を果たしていたとも言える。
ならば、こうした言葉の力、鼎談において張たちが語る言語の「呪術」性はどこからもたらされたのだろうか。
三浦雅士は、本特集で個人的には最も読み応えがあった論考「越境とは何か」において、「越境とはほんらいの自己という他者への越境であり、それこそ人類の特性」で、「人類が直立した瞬間は、そのまま越境の瞬間であった」と指摘する。
では、自己が他者であるとはいかなる事態なのか。三浦は、育児という行為に着目する。