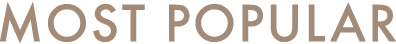三浦 単純に模倣とは言えないと思います。日本の洋画家たちはもちろん西洋に学んでいますが、自分の持っている感性と格闘して、それがオリジナルな形で強く表出されているものがやはり評価されるんじゃないかなと思います。
張 そもそも、わたしたちは何気なく日本音楽や東洋音楽、あるいはイスラム音楽といった言葉を使います。各国の文化が往還している時代に、こういった文化圏の名前を冠した音楽は現存しているのでしょうか。長木先生、いかがでしょうか。
長木 言葉としてはまだ生きていますが、大半が西洋化された音楽になってしまっています。例えば、1980年代ぐらいからいわゆる「ワールドミュージック」という言葉が盛んに言われるようになりました。
しかし、このワールドミュージックは基本的に西洋音楽ベースの和声構造とか旋律構造を前提にしている音楽です。例えば日本音楽についてヨーロッパの人に聞くと、久石譲などがその代表としてあげられるでしょう。
インドネシアのケチャのように、観光用にしかその地域の伝統音楽が残っていないということもありますが、それもそれで意味があるという捉え方もあります。
張 日本の音楽教育における西洋音楽の受容についてはいかがでしょう。
長木 日本の場合は、東京音楽学校が日本音楽をカリキュラムに導入したのが1930年代半ばで、これはナショナリズムと関わっています。それ以前の東京音楽学校では西洋音楽だけが教えられてきました。
明治前半まで、日本のそれまでの伝統音楽に親しんでいた人はドレミファソラシドを歌えなかったわけですが、明治期に入り近代国家の軍隊を作るうえでは、西洋音楽の音階を歌うことができ、それに合わせて行進できるということが重要視されました。
それからもう1つは、明治前半まで、当時の一般の人に親しまれていた歌舞音曲の類いは「河原者」とされた人々の行うものだったので、教育とマッチしなかった。つまり、世俗的な音楽が、社会階層という観点から近代国家の教育体制に合わなかったという事情がありました。
張 長木先生と三浦先生から、音楽や美術における還流についてお話しいただきました。
他方で、岡野道子先生の「ブラジル日系芸術家の肖像」と、佐藤麻衣先生の「他人種化する日系アメリカ人作家」についての論文を拝読して、絵画なら絵画、音楽なら音楽のみを極めようと海を渡った個人と、移民の芸術活動はやはり大きな違いがあるなというふうに思いました。
その点について、エリス先生いかがでしょうか。
エリス 境界の往還や越境というテーマは既に語り尽くされてきた感じもありますが、この特集を拝読して、具体的な葛藤の軌跡というのがいかに多様であるか、そして、個別的な体験にもとづいているのかということが立体的に見えてきました。
「渡っていく」といっても、多様な渡り方があります。社会集団を単位とした非常に太い境界の越え方もあれば、個人の身体レベルで越えられる細い境界もある。芸術に国境はないと言われているけれども、今回の論考を読んでいますと、これは一言で片づけられる問題ではないということを改めて感じました。